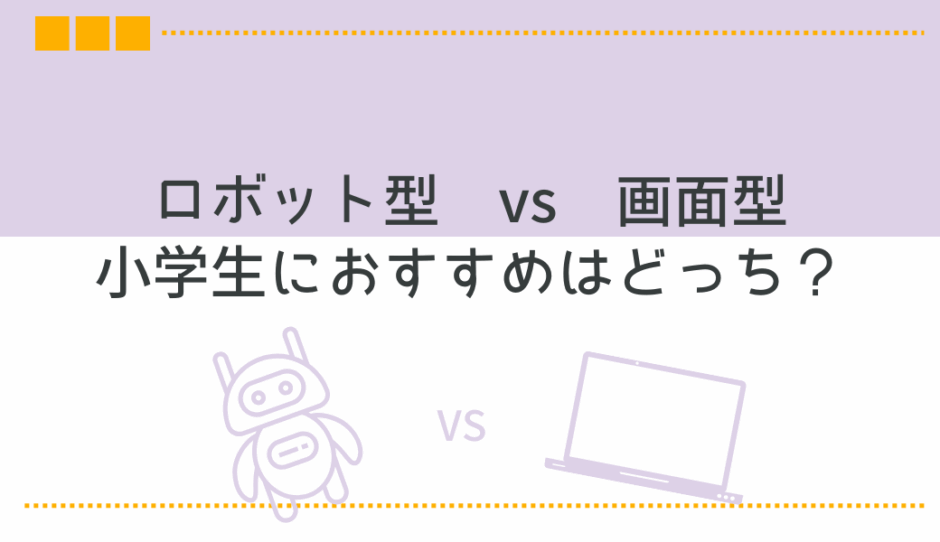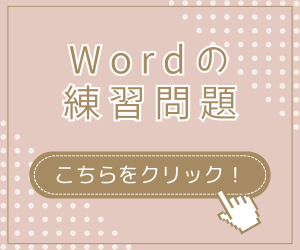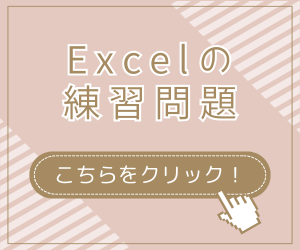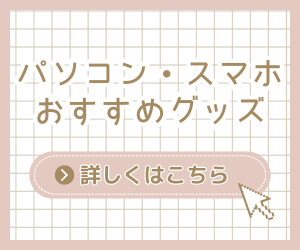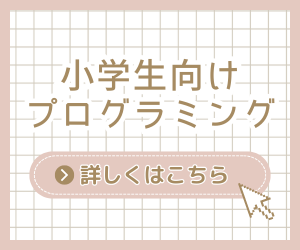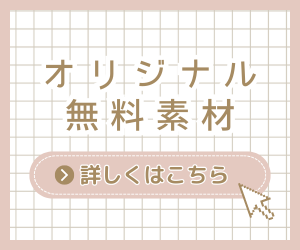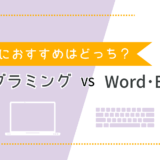子供の習い事にプログラミングが気になるけれど・・・
どのタイプのプログラミング教室を選べばいいの?
そんな疑問を持たれる保護者の方は多いのでないでしょうか?
プログラミング教室には、大きく分けて
- ロボットを組み立てて動かす「ハードウェア型プログラミング」
- 画面上で操作する「ソフトウェア型プログラミング」
の2つがあります。
ハードウェア型プログラミング(ロボット型)は、実際にブロックやパーツでロボットを組み立てて、プログラムを作って動かすスタイル。
ソフトウェア型プログラミング(画面型)は、パソコンやタブレットの画面上でScratchやマイクラのプログラミングなどを操作して、ゲームやアニメーションを作るスタイル。
どちらもプログラミン的思考を身につけることが目的ですが、学び方や楽しさのポイントは大きく異なります。

私はパソコン教室で勤務していた時に、低学年のお子様にプログラミングを教えていました。
そこで今回は、ハードウェア型プログラミング(ロボット型)とソフトウェア型プログラミング(画面型)のそれぞれの特徴や、メリット・デメリットを分かりやすく比較し、お子様に合ったプログラミング教室の選び方のポイントをお伝えしていきます。
- ブロックを組み立てて戦いごっこが好きなお子様
- スマホでゲームが好きなお子様
- マイクラに夢中のお子様
プログラミングで大きく成長する可能性が大!!なので、ぜひ、最後まで読んでみてくださいね。
ハードウェア型プログラミング(ロボット型)とは
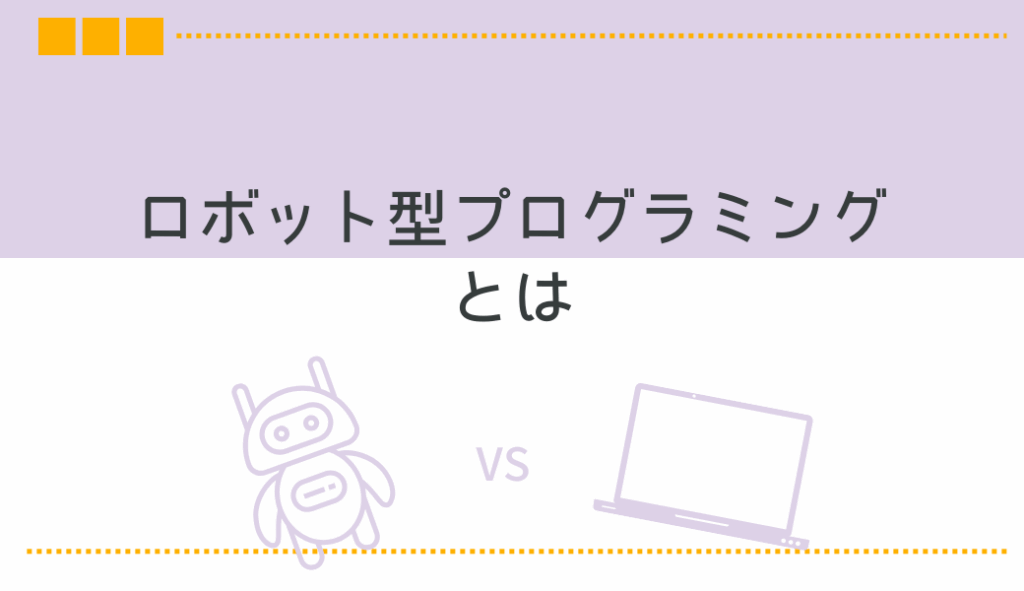
ハードウェア型プログラミングとは、ブロックやパーツを組み立ててロボットを作り、プログラミングで実際に動かす学習方法です。

手先が器用なお子様や、ものづくりが好きなお子様におすすめです!
子供たちは、モーターやセンサーを使って「前に進む」「障害物を避ける」「音を鳴らす」といった動きのプログラムを自分たちで作ります。

ファミレスでお料理を運んでくれるロボットが想像できるね!
自分の組み立てたロボットが動く瞬間は、子供たちにとって大きな達成感に繋がり、もっと色んなプログラムに挑戦してみたい!という「やる気」を引き出すきっかけになります。
ハードウェア型プログラミングのメリット
ハードウェア型プログラミングには下記のようなメリットがあります。
- お子様の「やる気」が持続しやすい
- 空間認識能力が身につく
- STEM教育につながる
ロボットを組み立てて動かすプログラミングは、画面上で操作するプログラミングと比べると、目に見えて分かりやすく、子供たちの達成感や感動が大きいです。
たとえ、ロボットが間違った動きをしたとしても、「自分でプログラムを作って動かした!」という感動につながるため、落ち込んだり飽きたりする可能性が低く、長く続けやすい傾向にあります。

我が家の下の子が初めてロボットを動かしたのは5歳の時でした!めちゃくちゃ感動してて可愛かったです(笑)
ロボットを組み立てる時は、何もないところから、ひとつひとつのブロックやパーツを立体的に組み立てていきます。
実際に自分の手で組み立てることによって、構造が理解でき、空間認識能力が身についていきます。

細かいパーツを組み立てる時もあるので、手先の器用さも向上しますね!
ハードウェア型プログラミングは、ロボットを組み立てて動かすだけでなく、Science(科学)・Technology(技術)・Engineering(工学)・Mathematics(数学)の学びにも直結しています。
・Science(科学)
センサーを使って「光や音」を検知する現象や、ロボットの動きから「力の伝わり方」や「摩擦」のような理科的な現象に触れることができます。
・Technology(技術)
プログラムを組み合わせてロボットを操作する過程で、「センサーとモーターをどのように連動させるか」といった情報技術の基礎を自然に体験できます。
・Engineering(工学)
ロボットを組み立てる際には、「どうすれば安定して動くか」「どの位置に部品をつければ効率的か」などを考える必要があり、工学的な発想や問題解決力が身につきます。
・Mathematics(数学)
角度や距離、繰り返し回数など、数学的な概念を「体験を通じて」学べます。たとえば、「90度回転するプログラム」を組んで実際に動かすと、算数で学ぶ角度の知識が現実と結びつきます。
このように、ハードウェア型プログラミングは、ロボットを組み立てて動かすことで、STEMの各分野をバランスよく体験できるのが大きな特徴です。
理数系が苦手かも!
というお子様も、遊びながら自然に学べる点が、多くの保護者に指示されている理由のひとつです。
ハードウェア型プログラミングのデメリット
ハードウェア型プログラミングには下記のようなデメリットがあります。
- 教材費が高め
- 小さいお子様は保護者のサポートが必要な場合がある
- 自宅でパーツを紛失・破損する可能性がある
ロボットを組み立てるためのブロックやパーツは、最初にまとめて購入する教室が多いです。
費用の目安は3万~5万円程度。子供習い事としては高額です。
また、カリキュラムが進むにつれて、パーツの追加購入が必要になる場合もあります。
月額4,000円台で自宅でプログラミング
個人差がありますが、小さいお子様は、慣れるまで保護者のサポートが必要になる場合があります。
私がパソコン教室でプログラミングを教えていた時は、小学2年生くらいから、まったく問題なく1人で受講できる子が多かったです。
年長や小学1年生でも、自分でテキストを読んでサクサク進めていける子もいてるので、どんな教室や教材が合うのか、無料体験などに参加して見極めてくださいね。
ロボットを組み立てるためのブロックやパーツを自宅に持ち帰ると、紛失や破損の可能性があります。
また、紛失や破損を防ぐために持ち帰りできない教室もあるので、自宅で自由に組み立てたり、復習したりということが難しい場合があります。
ソフトウェア型プログラミング(画面型)とは
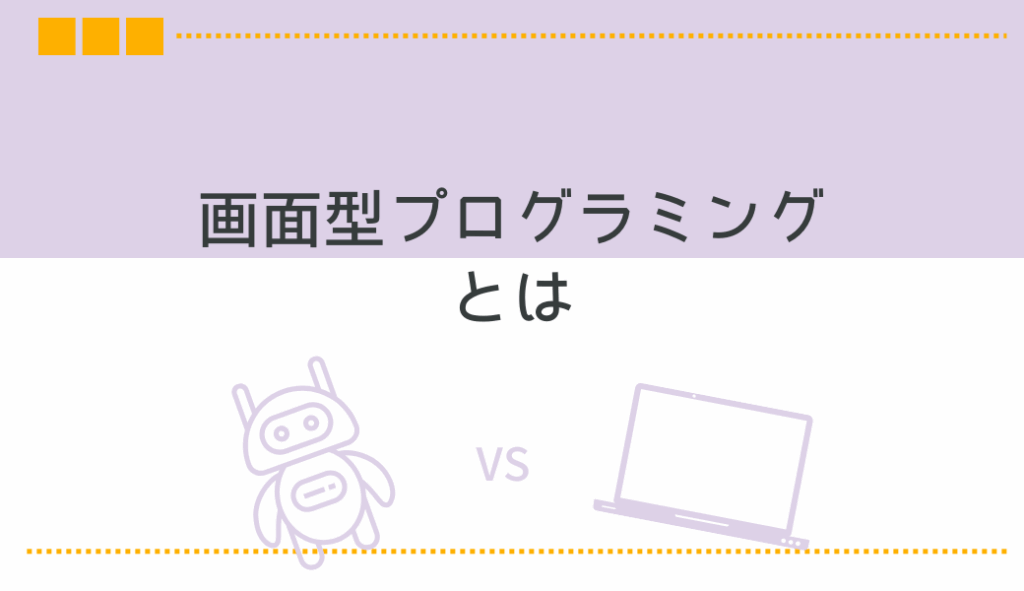
ソフトウェア型プログラミングとは、パソコンやタブレットの画面上で操作しながらプログラミングを学ぶ方法です。
代表的なプログラミング教材には、「Scratch」や「マイクラのプログラミング」などがあります。
子供向けに作られたプログラミング教材は、英語のコードを入力するのではなく、指示が書かれたカラフルなブロックを画面上で組み合わせてプログラムを作ります。
たとえば、「右に10歩進む」「スペースキーを押したら攻撃する」「もし敵に当たったら消える」といった動きを組み合わせて、直感的にゲームやアニメーションを作ることができます。

ゲームやアニメが好きなお子様や、自分の世界を想像して作り出すことが好きなお子様におすすめです!
ソフトウェア型プログラミングのメリット
ソフトウェア型プログラミングには下記のようなメリットがあります。
- 導入が手軽で繰り返し練習しやすい
- 想像力を活かせる
- 学校教育や将来の学びにつながる
ソフトウェア型プログラミングは、インターネットの環境とパソコンやタブレットがあれば、誰でも手軽に始められるので継続しやすいです。
「ビスケットプログラミング」や「Scratch」など、無料で利用できる教材もあるので、気になる方は、まずは、自宅で始めてみましょう。

ビスケットプログラミングは文字が読めない小さなお子様も始められるよ!
月額3980円~!100以上のコンテンツを自宅で学習
ソフトウェア型プログラミングは、画面上で操作をするため、ゲームやアニメーションなど自由に作ることができます。
背景を変えて独自の世界観を表現したり、キャラクターに会話をさせたり、BGMをつけたり、想像力次第で表現の幅が無限に広がります。

自分で描いたキャラクターを動かすこともできるよ!
ソフトウェア型プログラミングは、画面上でゲームやアニメーションを作るだけでなく、「論理的思考力」「創造力・想像力・表現力」「問題解決力」を育む教育的効果があります。
・論理的思考力
Scratchでは、「もし○○なら■■する」「繰り返す」といった条件分岐やループを多用します。これは、算数や数学で学ぶ論理構造に近く、考える順序を整理する力が自然に養われます。
・創造力・想像力・表現力
ゲームやアニメーションを通じて、自分のアイデアを形にすることができます。子供たちは「こう動かしたい」「こういうストーリーにしたい」と考え、試行錯誤しながら作品を完成させます。これは、作文や絵画と同じように、自己表現の手段として大きな価値があります。
・問題解決力
画面上で操作するプログラミングは、最初から思い通りに動くとは限りません。エラーや思いがけない挙動に出会った時、どこをどう直せば良いかを考える過程で、原因を探して改善する力が身につきます。
こような理由から、2020年から小学校で必修化された「プログラミング的思考」の授業では、Scratchのような画面型の教材が多く使われています。

自宅でScratchに慣れておけば、学校の授業でもスムーズに取り組めるね!

Scratchは、PythonやJavascriptなどの本格的なプログラミング言語へのステップアップにも繋がります。
ソフトウェア型プログラミングのデメリット
ソフトウェア型プログラミングには下記のようなデメリットがあります。
- 実物を触る体験がない
- 飽きやすい
- パソコンの操作が必要
ソフトウェア型プログラミングは、ロボットのように実物を触る体験がありません。構造を理解したり、空間認識能力を身につける点では、ロボットの方が向いています。
ソフトウェア型プログラミングは、ロボットと違って、目に見えて動く部分が小さいため、達成感や感動を感じにくく飽きやすいお子様もいます。

我が家の下の子は5歳の時にScratchに挑戦しましたが、画面上でキャラクターが動いても、動きが小さいのであまり感動せず、すぐに飽きてしまいました。

7歳になった今は、マイクラのプログラミングに夢中です(笑)
ソフトウェア型プログラミングは、ロボットに比べるとパソコンの操作が多く、基本操作を理解していないとスムーズに進められません。
そのため、マウスの操作が上手く出来なかったり、キーボードに慣れていないお子様は、戸惑ったり、イライラしてしまう事があります。
ロボット型と画面型の違いを比較
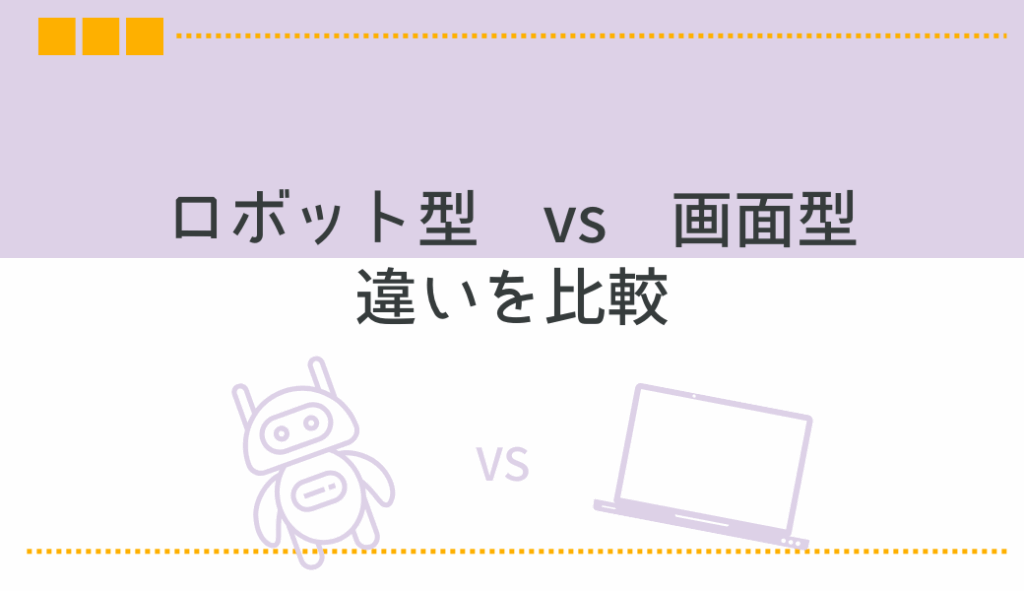
ハードウェア型プログラミング(画面型)とソフトウェア型プログラミング(画面型)、それぞれに強みと弱みがあります。
お子様の興味やご家庭の環境に合わせて、選ぶ時の参考になるように表にまとめて整理してみました。
| ハードウェア型プログラミング (ロボット型) | ソフトウェア型プログラミング (画面型) | |
|---|---|---|
| 学習方法 | ロボットを組み立てて プログラムで動かす | パソコンやタブレットの画面で操作して ゲームやアニメーションを作る |
| メリット | ・実物が動くので達成感や感動が大きい ・ものづくりの体験ができる ・STEM教育につながる | ・低コストで手軽に始めやすい ・自宅学習が可能 ・表現力や論理的思考力を育てやすい |
| デメリット | ・教材費が高め ・パーツの破損や紛失の可能性があるため、自宅で復習が難しいことも ・低学年はサポートが必要 | ・実物を触る体験がないので、構造や空間認識能力の理解が難しい ・動きがロボットに比べて小さいので飽きやすい ・PCの基本操作に慣れておく必要がある |
| 向いてる子 | ものづくりや工作が好きなお子様や、ブロックを組み立てて動かすのを楽しめるお子様 | ゲームやアニメに興味のあるお子様や、自分の世界を想像するのが好きなお子様 |
| 学習できる プログラミング 教室 | ・【日本最大級】ヒューマンアカデミーのロボット教室 ・IT×ものづくり教室リタリコワンダー | ・プログラミング教室数国内No.1!「QUREOプログラミング教室」 ・Codeland |小中高校生向け本格派プログラミングスクール |
ロボットは「組み立てて動かした子」、画面型は「デジタルで表現したい子」におすすめですが、どちらを選ぶかはお子様次第です。
迷った時は、両方とも体験して試してみましょう!

ほとんどのプログラミング教室で無料体験が実施されているよ!
どちらを選ぶ?保護者のチェックポイント
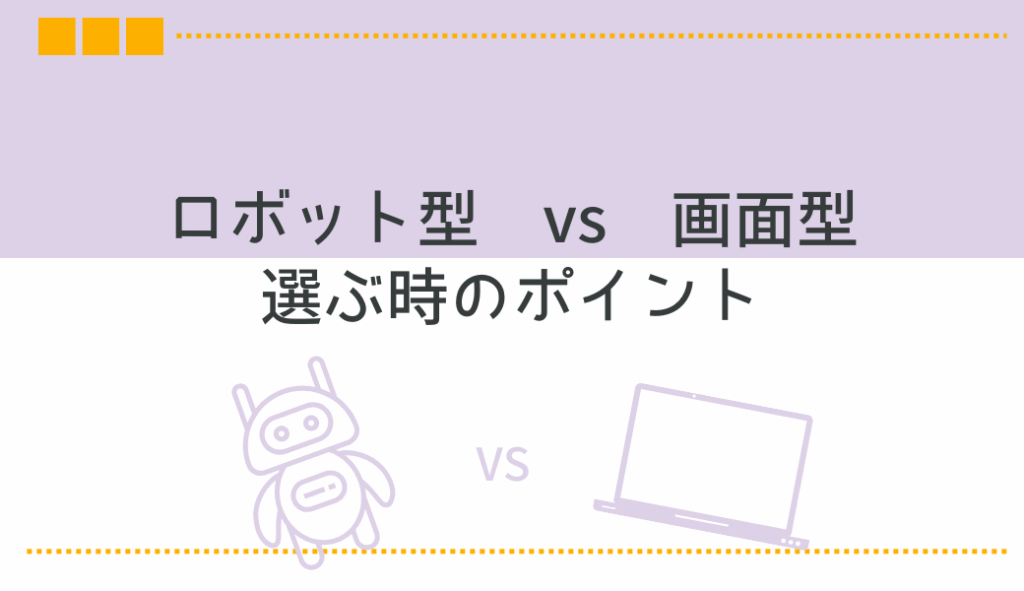
ハードウェア型プログラミング(ロボット形)とソフトウェア型プログラミング(画面型)、それぞれに魅力がありますが、最終的に選ぶのは、「お子様の性格や家庭の状況」によります。
ここでは、保護者の方が確認しておきたいチェックポイントをまどめました。
お子様の興味の入り口はどこか
・ものづくりや工作に夢中になるタイプ→ハードウェア型プログラミング(ロボット型)がおすすめ
・ゲームやデジタル表現に惹かれるタイプ→ソフトウェア型プログラミング(画面型)がおすすめ
お子様が普段どんな遊びに夢中になっているのかを観察すると、選びやすくなりますね!

我が家では、ブロックを組み立てて戦うのが好きな下の子はロボット型。絵を描いて物語りを作るのが好きな上の子は画面型が向いていました。
継続できそうかどうか
・「ロボットを組み立てるのが楽しい!」というお子様は、組み立てる作業自体がモチベーションになって継続しやすいです。
・「自分のアイデアを形にした!」というお子様は、ゲームやアニメを制作することで、達成感を得やすいです。
費用と環境のバランス
・ハードウェア型プログラミング(ロボット型)は、初期費用や教材費が高額になることが多いです。
また、ブロックやパーツの持ち帰りが不可で、自宅での復習が難しい場合もあります。
・ソフトウェア型プログラミング(画面型)は、インターネットの環境とパソコンやタブレットがあれば、プログラミング教室に通わなかったとしても、自宅での学習が可能です。

ぜひ、いろんなプログラミング教室の体験に行ってみて、お子様が楽しく続けられる教室を見つけてくださいね!
- 子どもが考える時間や個性を大切にしてくれるか
- 講師が一方的に授業を進めていないか
- 保護者にも丁寧に説明してくれるか
- 強引な勧誘がないか など
※目的や種類ごとに比較表にまとめました
まとめ
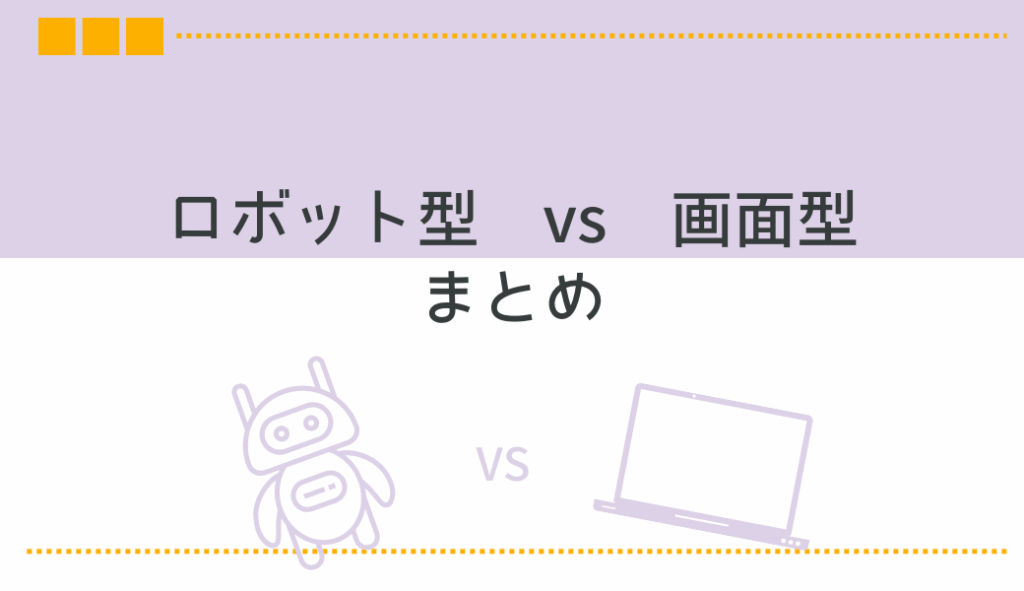
今回は、ハードウェア型プログラミング(ロボット型)とソフトウェア型プログラミング(画面型)の特徴や、メリット・デメリットを比較し、お子様に合ったプログラミング教室の選び方のポイントをお伝えしてきました。
ハードウェア型プログラミング(ロボット型)とソフトウェア型プログラミング(画面型)、どちらのプログラミング教室にも、それぞれの魅力と特徴があります。
実際にロボットを組み立てて動かす達成感や感動、STEM教育につながる学びが得られるのが大きなメリット。ものづくりや工作が好きなお子様におすすめです。
ゲームやアニメーションを通して、表現力や論理的思考力を伸ばしやすく、低コストで気軽に始めやすいのが魅力。デジタルに興味のあるお子様に向いています。
どちらを選んでも、「プログラミング的思考」を育てるという目的は同じです。
大切なのは、お子様が「楽しい!もっとやってみたい!」と思える環境を見つけることです。
迷った時は無料体験を利用してみよう
※目的や種類ごとに比較表にまとめました

無料体験での経験が、将来の学びにつながる大切な1歩になるはずです!
それでは、今日も最後まで読んでくださり、ありがとうございました☺