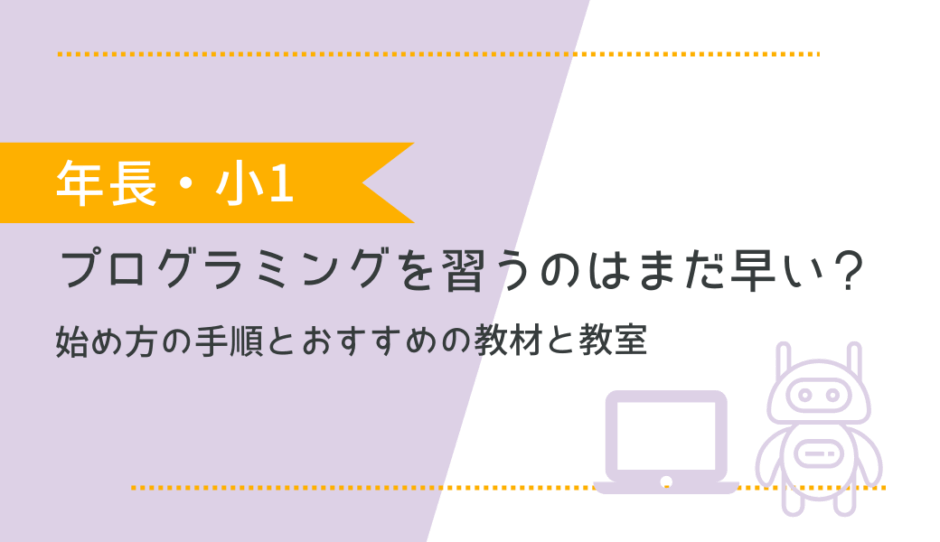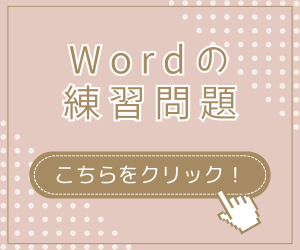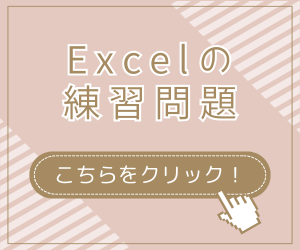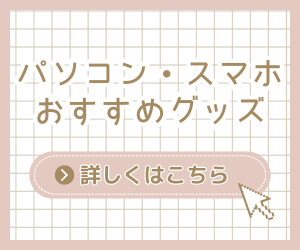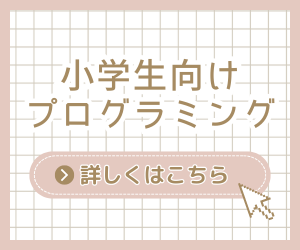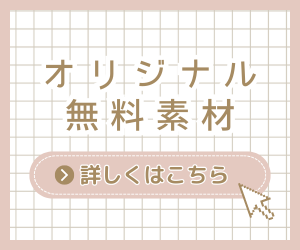記事内に商品プロモーションを含む場合があります
年長・小1の習い事にプログラミングってどうなの?
数年前からプログラミングが話題になっていますね。
お子様に人気の習い事として紹介されることが多く、検討されていらっしゃる親御さんも多いと思います。
しかし
プログラミングって本当に役に立つの?
小さい子供が習うには早すぎるんじゃない?
高い初期費用を払っても続かなかったらどうしょう?
など、不安に思われることもたくさんあると思います。
私は、パソコン教室で働いていた時に、年長から小学4年生の子にプログラミングを教えていました。
この記事では、実際に私がプログラミングの授業を行った経験から
- プログラミングは本当に役に立つのか
- 何歳から始められるのか
- 家庭での始め方とおすすめの教材
- 教室を選ぶ時の注意点
などについて詳しくご紹介していきます。

ぜひ、読んでみてくださいね。
なぜ今、子供の習い事にプログラミングが選ばれているのか?
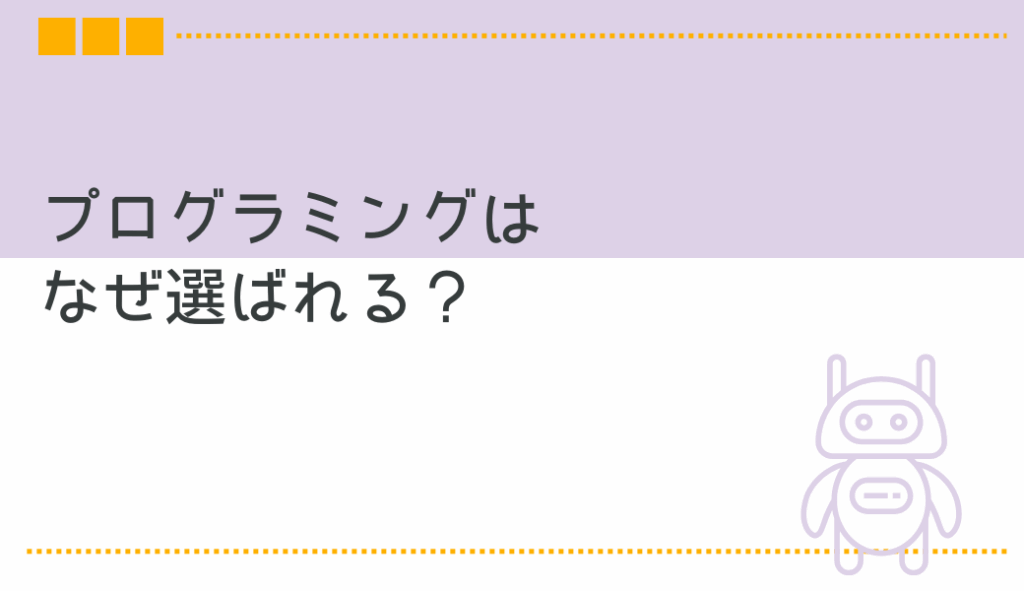
子供たちの未来(AI・IT社会)に役立つスキルとして、習い事にプログラミングが選ばれる時代になりました。
ここ数年でデジタル化が加速し、生成AIなどの技術もどんどん進化していると感じることはありませんか?
スーパーではセルフレジが普及し、飲食店ではタブレット端末でお料理をオーダーし、オーダーしたお料理はロボットが運んでくれるようになりました。
InstagramやTikTokでは、生成AIで作られた画像や動画がたくさん投稿されています。

急激に普及しすぎて、ちょっと怖く感じることもありますね。
子供たちが働く未来では、今よりももっとAIやITの技術が進化し、
- AIやITを活用している人や企業
- AIやITを活用していない人や企業
では、明確な差が出ていることが予想されます。
そんな未来で、子供たちがAIやITを活用する側の人間になるために、「今」始める習い事としてプログラミングが選ばれています。

未来のために「今」始めることで差がつくかも知れないんだね。

個人的な意見としては、子供たちにはWordやExcelよりプログラミングを習ってほしいです。
今まで私たちがWordやExcelで作成していた書類も、すでに生成AIで作れるようになってきました。
これからの子供たちがプログラミングを学ばなかった場合、非常に不利になるのではないかと私は感じています。
そもそもプログラミングとは
プログラミングとはコンピューターに対する指示を作る作業のことを言います。
直感で指示を出したり、なんとなくで指示を出しても、思い通りにコンピューターは動いてくれません。
コンピューターを思い通りに動かすためには
- 論理的思考力
- 創造力と想像力
- 問題解決能力
などをプログラミング学習を通じて身につける必要があります。
論理的思考力
論理的思考とは、目的を達成するために物事を分析して整理し、順序立てて筋道を立てる思考法のことです。

簡単に言うと、「無駄なく、正確に考える力」です。
この論理的思考力は、プログラミングを学習することで自然と身についてきます。
これは、プログラミングが「どうすれば思い通りに動くのか」を考える活動だからです。
とくに、6歳~10歳くらいの子供さんは、論理的思考の基礎が育つ時期と言われるので、プログラミングを学習することが将来的な思考力の土台作りになります。

論理的思考力は、料理をしたり計画を立てたり、日常生活でも役立ちます。
創造力と想像力
プログラミングにおける創造力とは、まったく新しいものを自分のアイデアで生み出す力です。
たとえば、
- 空を飛ぶ魚のゲームを作りたい
- 猫が海の中を探検する物語を作りたい
など、プログラミングは自分の中にあるアイデアを実際に見えるものにしていく創造の体験です。
一方で、想像力とは、未来や他人の気持ちなど、見えない仕組みを思い描く力です。
プログラミングをしていると
「このキャラクターは、どんな動きにしたら皆が見てくれるだろう?」
「どうすればもっと楽しいゲームになるだろう」
など、相手の気持ちや未来の動きを想像する場面がたくさん出てきます。
こういった経験を積むことで、他人の目線で考える力や、先の展開を考える力が自然と身についてきます。

プログラミングは、子供さんの「考える楽しさ」や「つくる喜び」を広げてくれるツールでもあります。
問題解決能力
プログラミングにおける問題解決力とは
- 問題の原因を見つけて
- どうすれば解決できるかを考え
- 実際に行動できる力
のことです。
これは、現実世界でも非常に役に立つ「生きる力」とも言われています。
プログラミングをしていると、小さなエラーを自分の力で解決する機会がたくさん出てきます。
小さなミスや試行錯誤を繰り返す中で、子どもたちは知らず知らずのうちに「どうしたらうまくいくのか?」を考えて、「つまづいた時にどう立ち向かうのか」という問題解決力が身についてきます。
プログラミングは何歳から始められる?
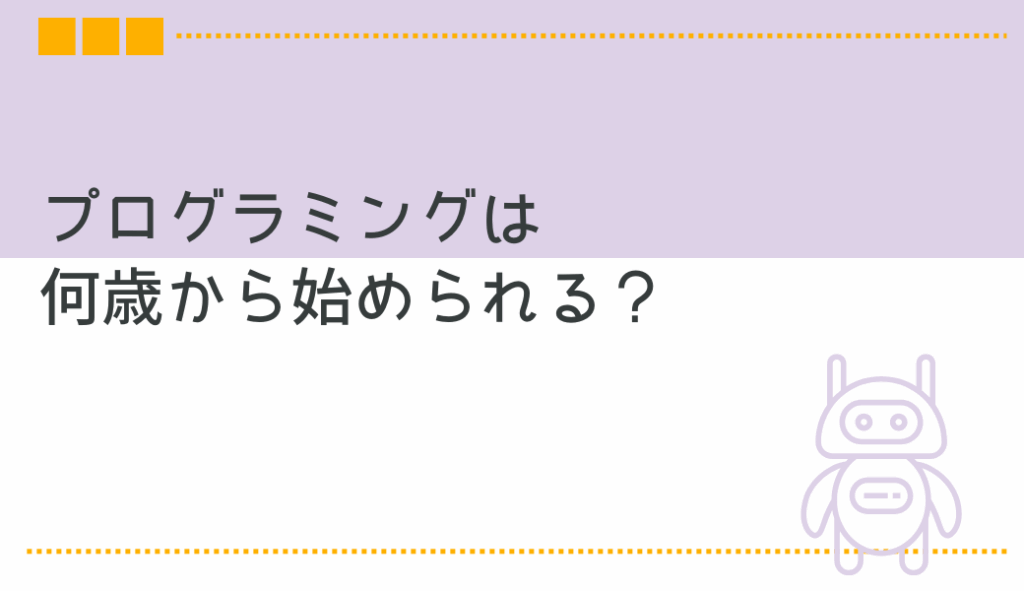
では実際に、プログラミングは何歳から始めることができるでしょうか。
年長・小1から始められる
プログラミングは、年長・小1から始めることができます。
我が家の子供たちがプログラミングを始めた年齢は、上の子が6歳、下の子が4歳です。

文字が読めなくても大丈夫!
小さいお子様が学習できるプログラミング教材もいくつかあって、代表的なものには「ビスケットプログラミング」や「scratchジュニア」があります。
どちらもタブレットやパソコンなどの端末とインターネット環境があれば、無料で使用することができます。
我が家の子供たちも「ビスケットプログラミング」から始めました。
「ビスケットプログラミング」は小さいお子様向けに開発されたプログラミング教材ですが、奥が深く、大人も楽しめるような設計になっています。
操作方法もとても簡単なので、お子様がスマホやタブレットに興味をお持ちでしたら、ぜひ、一緒に始めてみてほしいです。
年長・小1から始めるメリット
年長・小1からプログラミングを始めるメリットは、個人差もありますが、論理的思考力や問題解決能力が自然に身につきやすいという点です。

特に、論理的思考力の基礎になる部分がしっかり成長していると感じました。
子供と一緒におうちではじめてみよう!
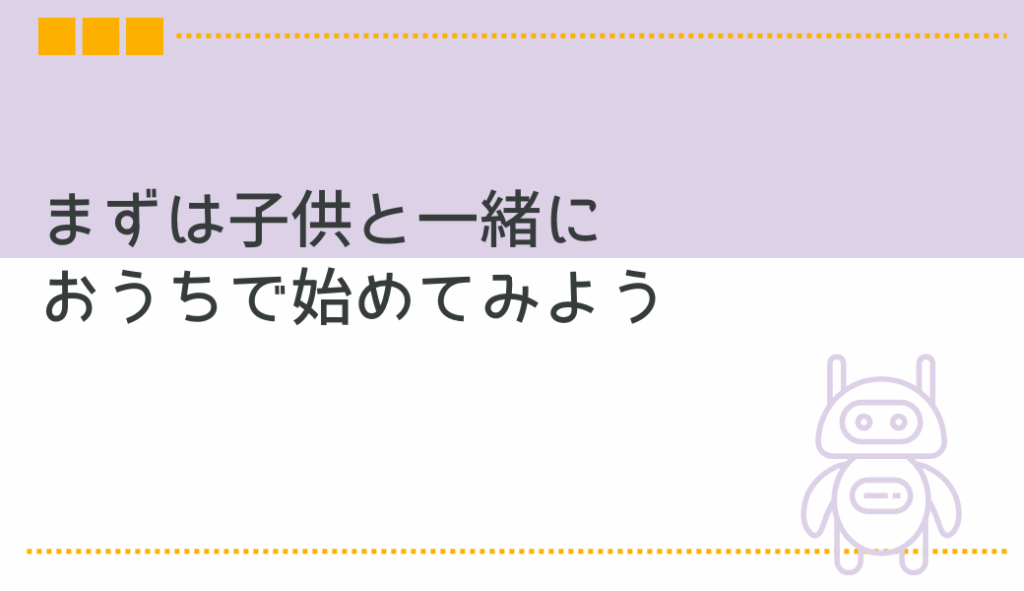
年長・小1のお子様がプログラミングを始める場合、まずは、保護者の方と一緒におうちで始めてみるのがおすすめです。
プログラミングは安い習い事ではなく、平均して月謝は1万円前後~3万円、それ以外にも入会金や教材費が別途かかる場合もあります。
いくら教材やカリキュラムが素晴らしくても、お子様の興味が薄かったり、50分~60分の授業時間を集中できなかったりすると継続は難しいです。
まずは少しずつ、保護者の方と一緒にゲーム感覚で楽しんでみましょう。
- すでにスマホやタブレットでゲームを楽しんでいる
- マイクラに夢中
というお子様は、プログラミング教室の体験などにどんどん行ってみるのもおすすめです!
※目的や種類ごとにピックアップ

マイクラのキャラクターをプログラミングで動かす教室も増えてきているので、記事の後半で紹介していきますね!
おうちでプログラミングを始める場合は
- ビスケットプログラミング
- Scratchジュニア
- Scratch
が無料で始められるのでおすすめです。
これらのツールを試してみて、お子様の興味がどんどん強くなって、50~60分の授業を集中して受けれそうだなと感じた時が、プログラミングを習い始める目安のひとつになります。

プログラミングと一緒にタイピングの練習も始めると、よりスキルアップに繋がります!
月額3,316円~100以上のコンテンツが自宅で学べる
ビスケットプログラミング
初めてプログラミングを触るお子様におすすめなのはビスケットプログラミングです。
アプリのダウンロードやアカウント登録の必要がなく、直感的な操作で手軽に始められるところが魅力です。

ビスケットプログラミング
- 4歳~
- ブラウザとアプリの両方あり
- スマホ・タブレット・パソコンに対応
- アカウント不要

ビスケットプログラミングは自分で描いた絵をプログラミングで動かします。
まずは、丸や三角、星など、簡単な図形を描いて動かしてみましょう。
右に動かすにはどうすれば良いか?
上に動かすにはどうすれば良いか?
論理的思考力の一番基本的な考え方が育ちます。
ためしに、ビスケットプログラミングで海の中を作ってみるとこんな感じになります。
魚の泳ぐ方向やスピード、泡がゆらゆらと揺れる様子、これらの動きをプログラミングで作っています。
ビスケットプログラミングは非常にシンプルな設計になっていますが、アイデア次第で物語やゲームなど作れるものは無限大です!
私は、ビスケットプログラミングを授業で教える中で、創造力と想像力が大きく成長すると感じました。
- 種からお花が咲く物語り
- ゴミを掃除するお掃除ロボット
- 宇宙人をやっつけるシューティングゲーム
- 動く観覧車
- 着せ替え
など、こちらが何かを提案しなくても、子供たちはどんどん作っていくので驚かされました。
ビスケットプログラミングの公式サイトには、操作方法の説明がありますが、書籍を1冊だけ購入してじっくり挑戦するのもおすすめです。
Scratchジュニア
Scratchジュニアも文字が読めなくても始められるプログラミングです。
画面上で、ブロックを組み立てて動きの指示を作っていくので、ビスケットプログラミングよりも1歩進んだプログラムを作ることができます。
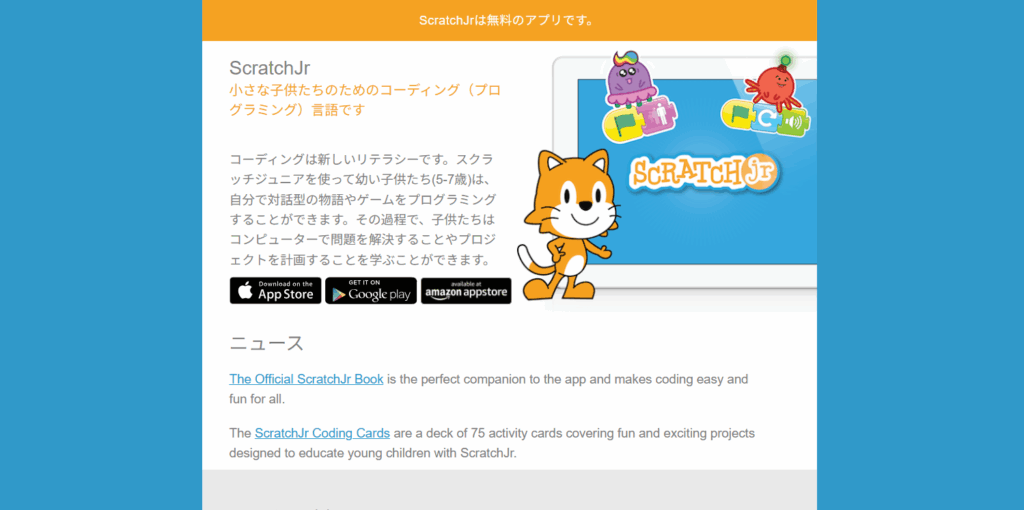
Scratchジュニア
- 5歳~7歳
- アプリのダウンロードが必要
- iPadやAndroidのタブレット端末に対応(パソコン不可)
- アカウント不要
我が家の子供たちもScratchジュニアを楽しんでいます。
アプリをダウンロードしておくと、ちょっとした待ち時間などにも使えるので便利です。

Scratchジュニアの画面も直感的に操作できるので分かりやすいです。
Scratch
Scratchは、Scratchジュニアがさらに進んだバージョンで、ひらがなが読めるお子様から対象になります。
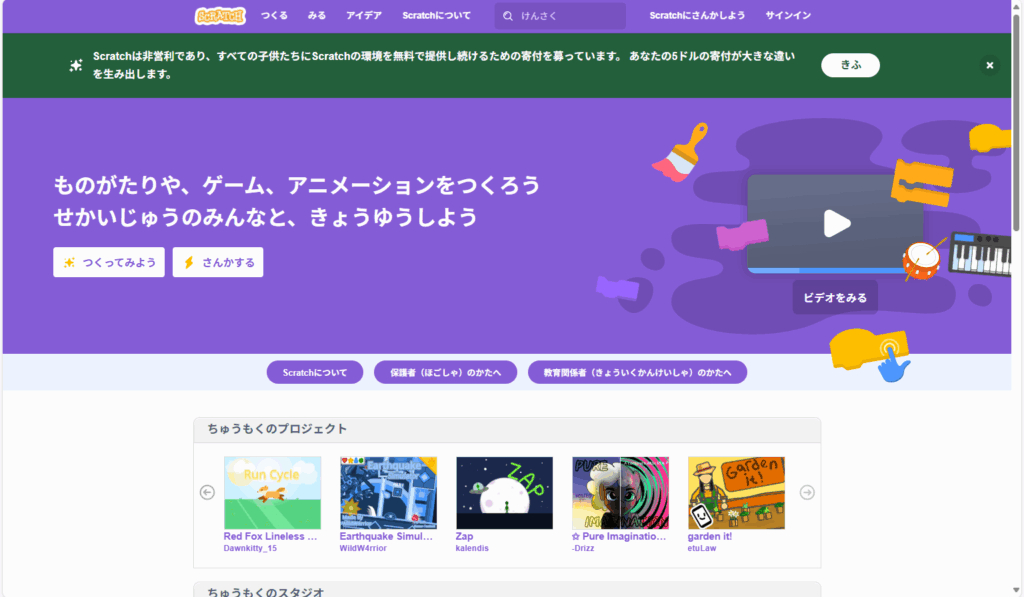
Scratch
- 8歳~16歳
- ダウンロード不要。Windows版のアプリもあり。
- スマホ・タブレット・パソコンに対応
- アカウント不要
(作った作品をweb上に保存・共有する場合は必要)
画面上でブロックを組み立てて動きの指示を作る仕組みは、Scratchジュニアと同じですが、単純な動きから複雑な動きまで、かなり細かい指示を作ることができます。
また、大きさを変化させる時に%で指示をしたり、場所を指定する時に座標を使ったり、曲がる時に角度を指示したりと、数学的な要素も自然に学習することができます。
対象年齢は8歳~が推奨されていますが、好きな子は6歳くらいからサクサク操作をしていました。
Scratchでは、
- オリジナルゲームの作成
- アニメーションの作成
- 音楽・アート作品の作成
など、しっかりプログラミングを学習することができます。
また、PythonやJavascriptなどの本格的なプログラミング言語へのステップアップにもつながります。

プログラミング検定もあるので、目に見える形で結果を残すことも出来ます!
子供向けのプログラミング教室の種類

ここ数年で子供向けのプログラミング教室はかなり増えました。
子供向けのプログラミング教室は大きく分けて
- 画面上で操作する「ソフトウェア型プログラミング」
- ロボットを組み立てて動かす「ハードウェア型プログラミング」
の2つに分かれます。
どちらがお子様に合うかは、体験教室などで実際に体験してみて判断するのがおすすめです。
我が家の子供たちは、娘はどちらも楽しんで取り組んでいますが、息子が年長の時は、圧倒的に「ハードウェア型プログラミング」の方が好きで、集中して取り組んでいます。
ソフトウェア型プログラミング
ソフトウェア型プログラミングは、「ビスケットプログラミング」や「Scratch」のように画面上で操作をするプログラミングです。
シンプルな操作のため、初心者やご家庭でも取り組みやすく、長く続けやすい傾向にあります。
最近では、マイクラのプログラミングが出来る教室が増えているので、小さいお子様もより学習しやすくなっています。

ソフトウェア型のプログラミングに集中できなかった息子も、マイクラのプログラミングが出来るようになってどんどん集中して取り組むようになりました!
マイクラを取り入れているプログラミング教室
- リタリコワンダー
(教室受講・オンライン受講の両方あり)
- 【話題沸騰中】ヒューマンアカデミーのプログラミング教室(対面型の教室受講)
- Codeland
(オンライン受講)
- マイクラの習い事【Tech Teacher Kids】(オンライン受講)
- 【AD】デジタネ(自宅で学習するためのオンライン教材)低価格で始められるのでおすすめ!
ハードウェア型プログラミング
ハードウェア型プログラミングは、実際にロボットやセンサーなどの部品を組み立てて操作するプログラミングです。
実際に自分の手で組み立てることによって、構造が理解でき、空間認識能力が身についてきます。
組み立てるための部品は基本的に購入する必要があるので、ソフトウェア型プログラミングよりも初期費用がかかります。

立体的なロボットを動かす時は、画面上のキャラクターを動かす時と考え方が違ってくるよ!
月額4000円台で自宅でロボットプログラミング
プログラミング教室を選ぶ時の注意点

プログラミング教室を選ぶときは、いくつかのポイントと注意点があります。
まずは、何年も長く通い続けることを前提にして
- 入会金や月謝、テキスト代、部品代などの費用
- 回数、曜日、時間帯、立地などの通いやすさ
を確認しましょう。
特に、ロボットプログラミング教室では、カリキュラムが進むにつれて、部品の追加購入が必要になる場合があります。
他にも、
- 講師と生徒の人数
- 講師の対応
なども注意しておきましょう。
講師と生徒の人数
年長や小1の小さい子供さんがプログラミング教室に通う場合、講師が1人で対応できる人数は限られています。
私が授業をしてきた経験から言うと、1人で対応できる人数は多くても5人までかなと感じました。
大人の授業対応と同時進行
珍しいパターンでは、大人のofficeの授業と、子供のプログラミングの授業を1人の講師が同時進行している教室もありました。
これは確実に小さい子供に手が回りません。
また、知らない大人がいることで、伸び伸びとプログラミングを学べない子供さんもいます。
マンツーマン対応と少人数制
基本的には少人数制の教室が多いと思いますが、マンツーマン対応をしてくれる教室もあります。
マンツーマンなら細かいところまで丁寧にフォローすることができるので、知識は非常に身につきやすいです。
しかし、子供さんの性格によっては、一緒に学ぶ仲間がいた方が相乗効果でお互いにスキルアップできるという子もいます。

どちらがお子様に合うかは、体験してみて判断するといいよね!
講師の対応
これが一番大事なポイントです!
同じ教材を使用して同じカリキュラムを進めたとしても、知識が身につくかどうかは、講師の対応で180度変わります。
中には、子供の気持ちに寄り添わず、テキストを業務的に進めてしまう講師もいます。
また、そもそもプログラミングの必要性を理解しておらず、知識の浅い講師もいます。
ネット上の口コミは当てにならない場合もあるので、実際に無料体験やお試し授業などを受けて、しっかり見極めるようにしましょう。

見極めるためには、たくさん質問することが大切だよ。

丁寧に説明してもらえるかどうか、知っていることでも質問してみるといいですね!

無理な勧誘をして来ないかどうかもポイントかな!
年長・小1から通えるプログラミング教室

年長・小1から通えるプログラミング教室をピックアップしてみました。
※目的や種類ごとにピックアップ
マイクラの習い事【テックマイン】

テックマインの特徴
サバイバルやクリエイティブ、コマンドなど、マインクラフトでの「遊び」を「学び」に変えるオンライン受講の習い事。プレイを通じて、ITスキルやプログラミング思考が自然と身につくカリキュラム。初月はマンツーマンの手厚いサポートがあるので、年長や小1の小さいお子様も安心。
| 対象年齢 | 5歳~ |
| 入会金 | 11,000円~ |
| 月謝 | 11,000円~ |
| 受講方法 | オンラインで受講(少人数制) |
| 回数・時間 | 1回60分×月4回~ |
| 使用する教材 | マイクラ・Javascriptなど |
| おすすめな人 | マイクラが好きなお子様 |
| 公式サイト | マイクラの習い事【Tech Teacher Kids】 |
※60分の体験授業が無料!!

マイクラが好きなお子様ためのプログラミング教室かも☺
リタリコワンダー
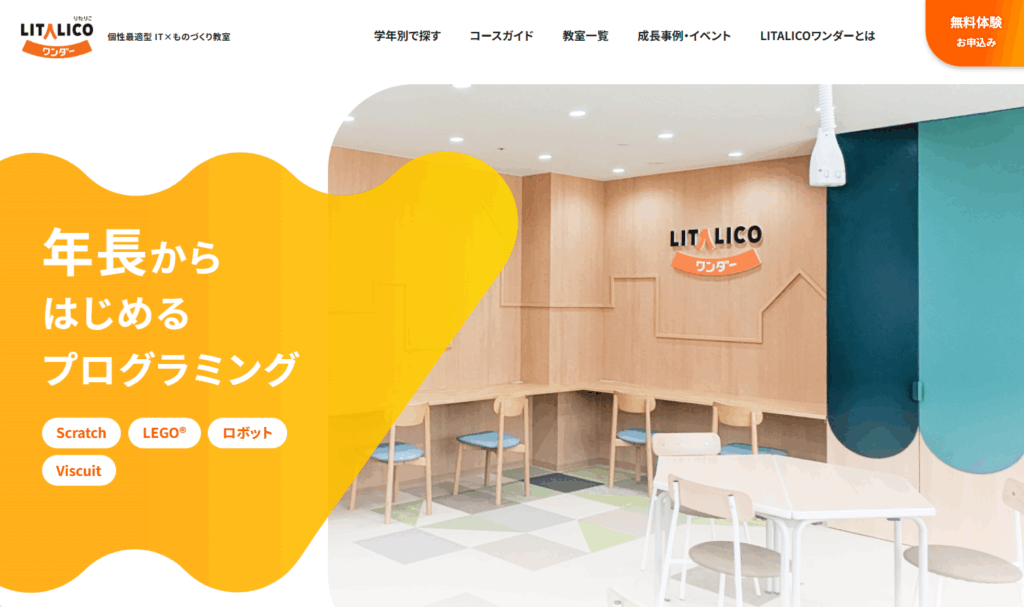
リタリコワンダーの特徴
個性最適型IT×ものづくり教室で、お子様1人ひとりに合わせたオーダーメイドカリキュラムを提供。
学習面やコミュニケーションに不安のあるお子様も安心して通える。
オンラインと対面型の両方あり。
| 対象年齢 | 年長~高校生 |
| 入会金 | 16,500円~ |
| 月謝 | 教室受講:29,700円~ オンライン:33,000円~ |
| 受講方法 | 対面型の教室受講(少人数制)とオンラインで受講(マンツーマン)の両方あり。 |
| 回数・時間 | 教室受講:1回90分×月4回~ オンライン:1回60分×月4回~ |
| 使用する教材 | ビスケットプログラミング・scratch・マイクラなど |
| おすすめな人 | オーダーメイドカリキュラムで手厚いサポートが必要なお子様 |
| 公式サイト | IT×ものづくり教室LITALICOワンダー |
リタリコワンダーは費用が高額な分、とても手厚いサポートが受けられます。特にオンライン受講はマンツーマンの個別対応です。高学年くらいになると、本格的なプログラミング言語で3Dゲーム制作などのカリキュラムもあります。
※60分の体験授業が無料!!

ヒューマンアカデミーのロボット教室
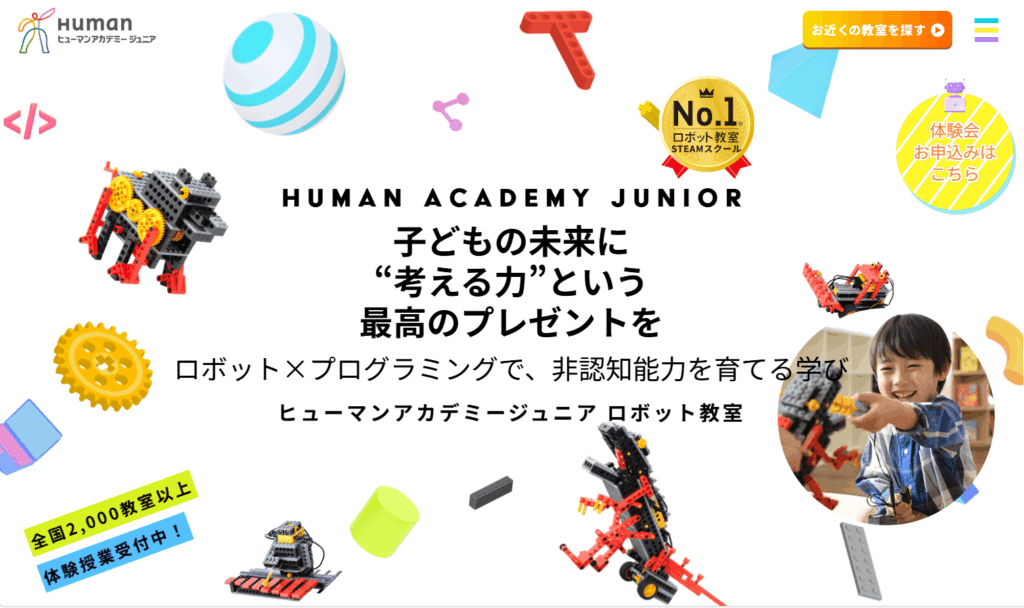
ヒューマンアカデミーのロボット教室の特徴
全国2000教室以上で、累計生徒数が10万人を超える実績のあるロボット教室。
5つのコースでお子様の年齢やスキルに合わせて段階的にレベルアップしていける。
ロボットクリエイター「高橋智隆先生」が教材を監修しているので安心感がある。
| 対象年齢 | 年中~(教室によって異なる) |
| 入会金 | 11,000円 |
| 月謝 | 11,550円 |
| 受講方法 | 対面型の教室受講 |
| 初期費用 | 33,000円 |
| 回数・時間 | 1回90分×2回 |
| 使用する教材 | オリジナル教材 |
| おすすめな人 | ロボットプログラミングに興味のあるお子様 |
| 公式サイト | 【日本最大級】ヒューマンアカデミーのロボット教室 |
Z会プログラミング講座

Z会プログラミング講座の特徴
自宅でロボットも学べるZ会のプログラミング講座。半透明のブロックが可愛らしく女の子にもおすすめ。テキストがとても分かりやすいという口コミが多いので小さいお子様も安心。プログラミングがまったく初めての小さいお子様には、全3回の「プログラミングはじめてみる講座」も用意されている。
| 対象年齢 | 年長~ |
| 月謝 | 4,683円~ |
| 受講方法 | 自宅で自主学習 |
| 回数・時間 | 好きな時間に好きなだけ |
| 使用する教材 | オリジナル教材・ロボットなど |
| おすすめな人 | 自宅でロボットやプログラミングを学びたいお子様 |
| 公式サイト | 自宅でプログラミングを学ぶ/Z会プログラミング講座 |
※無料で資料請求!
デジダネ


デジダネの特徴
YouTuber風の先生が解説する動画スタイルで、マイクラやRoblox(ロブロックス)を使い、ゲームを作りながらプログラミングを学べるオンライン学習教材。100以上のレッスンが月額3,316円(税込)から自宅で学び放題。インターネットの正しい使い方を学ぶコンテンツがあることも魅力。
| 対象年齢 | 小学1年生~ |
| 月謝 | 月額3,316円~(年払いコースの場合) |
| 受講方法 | 自宅で自主学習のオンライン教材 |
| 回数・時間 | オンライン教材で学び放題 |
| 使用する教材 | ディズニー・scratch・マイクラなど |
| おすすめな人 | いろんなプログラミング教材を好きなだけ試してみたいお子様 |
| 公式サイト | 【AD】オンラインで学ぶ!小中学生向けプログラミング「デジタネ」 |

インターネットの正しい知識を学べるコンテンツがあるのは貴重!

デジタネの無料体験は、メールアドレスの登録とパスワードの設定のみで、すぐに始められます☺
※14日間の体験が無料!
Code of genius

Code of geniusの特徴
本格的なプログラミングを学べる小学生向けのオンライン講座。
低学年のコースでは、その学年に特化した講師が丁寧に指導。
小学生だけでなく、中学生、高校生まで学習できる充実したカリキュラムがあり、年に1回、全国の生徒とオンラインで作品の発表会なども開催。
| 対象年齢 | 小学1年生~ |
| 入会金 | 11,000円前後 |
| 月謝 | 11,000円~ |
| 受講方法 | オンラインで受講 |
| 回数・時間 | 1回60分×月4回~ |
| 使用する教材 | scratch、TechTimeなど |
| 公式サイト | Code of genius Jr.(コードオブジニアスジュニア) |
Code of genius Jr.(コードオブジニアスジュニア)

Code of genius Jr.(コードオブジニアスジュニア)の体験授業は1,100円必要ですが、入会する時の入会金に充当されます。
Code land

Code landの特徴
完全マンツーマンでプログラミングを学べる子供向けのオンライン講座。
マイクラのプログラミングがあるので、低学年のお子様も始めやすく、PythonやUnityなど高校生まで学習できる充実したカリキュラムが特徴。月4回コースだけでなく、月2回コースがあるので、低学年のお子様も無理なく始められる。

急な体調不良の振替にも柔軟に対応してくれます!
年長・小1のプログラミングのまとめ
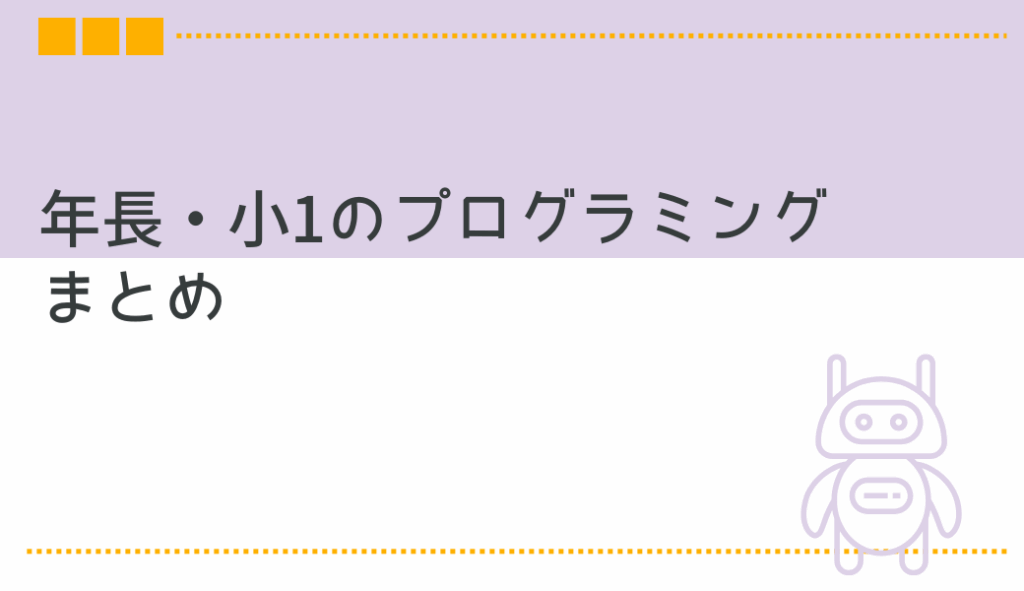
今回は、年長・小1からのプログラミング教室についてまとめました。
未来のAI・IT社会に対応していくためには、今から少しずつプログラミングを学習することが大切です。
年長・小1の小さい子供さんでも、ゲームやマイクラに興味を持っているなら、ぜひ、プログラミング学習を始めてほしいです。
最初はなかなか集中できなくても、いつの間にか「こんなことも出来るようになったの?」と驚かされるくらい成長してくれます☺
年長・小1から通えるプログラミング教室もどんどん増えているので、ぜひ、体験教室などに行ってみてくださいね!
※目的や種類ごとにピックアップ
それでは、最後まで読んでくださり、ありがとうございました☺