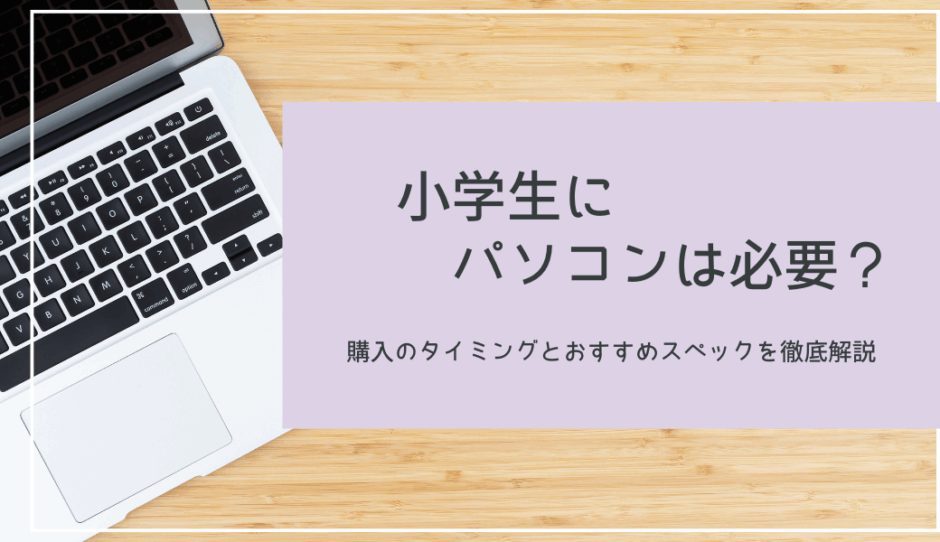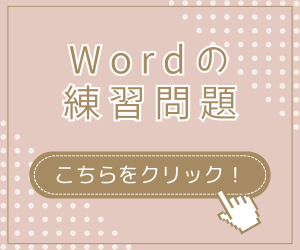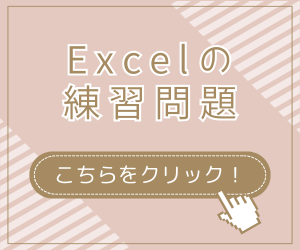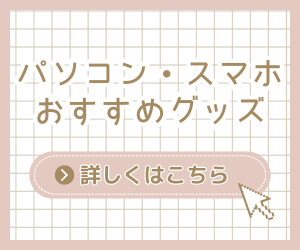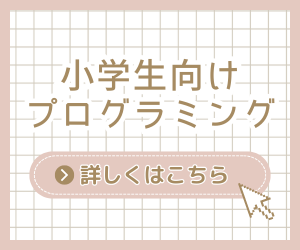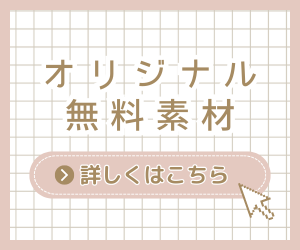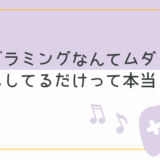記事内に商品プロモーションを含む場合があります
小学生の子供にパソコンを購入するべき?
最近は、このような悩みを抱える保護者の方が増えています。
ここ数年でデジタル化社会が急速に進化し、学校教育が変化してきました。
小学校でも1人1台のパソコンやタブレットが配布され、プログラミング教育の必修化や調べ学習の拡大、家庭でもパソコンの必要性を感じる場面が増えてきています。

やっぱり子供用のパソコンが1台あると便利だね。
とはいえ、いざ購入するとなると
いつ買うのが良いの?
どんなパソコンを選べば安心?
学校で配布されるパソコンだけではダメ?
など、悩んでしまいますよね。
そこで今回は、
- 小学生にパソコンは本当に必要なのか
- 購入のタイミングや判断基準
- 小学生向けのおすすめスペック
について、詳しく解説していきます。

我が家では、上の子(娘)が年長の時に、子供用にパソコンを1台購入しました。

その時の体験も含めて解説していきますので、ぜひ、最後まで読んでみてくださいね!
小学生にパソコンを購入する家庭が増えている背景
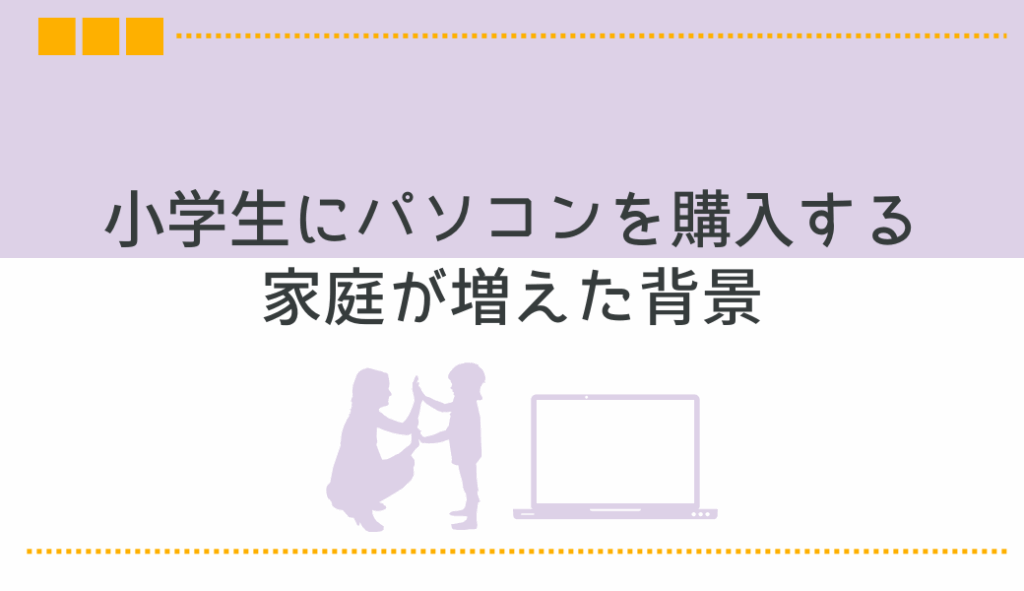
ここ数年で「小学生にパソコンを購入する家庭」が一気に増えてきました。
その背景には、大きく以下のような理由があります。
- 学校でのICT教育の拡大
- プログラミング教育の必修化
学校でのICT教育の拡大
2020年度から始まった文部科学省の「GIGAスクール構想」により、全国の小中学校で1人1台のパソコンやタブレット端末が整備されました。
これにより、子供たちは日々の授業や宿題の中で自然にパソコンを使う機会が増えてきています。
具体的には、
- 調べ学習でインターネットを使う
- GoogleドキュメントやWordで文章をまとめる
- PowerPointで発表資料を作る
- 学習アプリで漢字や算数を練習する
などです。
ただし、学校で配布されるパソコンやタブレット端末には、フィルタリングや使用制限があるため、学校の授業や宿題以外の発展的な学習には使えないことが多いです。
たとえば、
タイピングのアプリをいろいろ試してみたい!
プログラミングで作ったアニメーションを共有したい!
ペイント以外のソフトで本格的にお絵描きがしたい!
ということには使えない可能性が高いのです。
このことから、学校で配布されるパソコンは学校の授業や宿題用、学校の授業以外に自宅で学習を発展させたいお子様はパソコンを1台購入という判断をされるご家庭が多いです。
プログラミング教育の必修化
2020年度から、小学校でプログラミング教育が必修化されました。
といっても「コードを書いてプログラマーを育てる」ことが目的ではありません。
文部科学省が掲げる狙いは、プログラミング的思考を育てることです。
プログラミング的思考とは、
- 複雑な課題を小さな手順に分けて考える
- 「もし〇〇なら△△する」という条件を整理する
- 試行錯誤しながら改善していく
といった、論理的に考え、解決策を組み立てていく力を指します。
これには、Scratch(スクラッチ)などのプログラミング教材が使われることが多く、子供たちはゲームやアニメーションを作るプロセスを通じて、プログラミング的思考を身につけていきます。
こうした背景から、学校での授業だけでなく 「家庭でも自由にプログラミングに触れさせたい」 と考える保護者が増え、結果的にパソコンを購入する家庭が増えているのです。
小学生におすすめのプログラミング教室を項目別にまとめました
パソコンはいつ買うのが良い?購入の判断基準
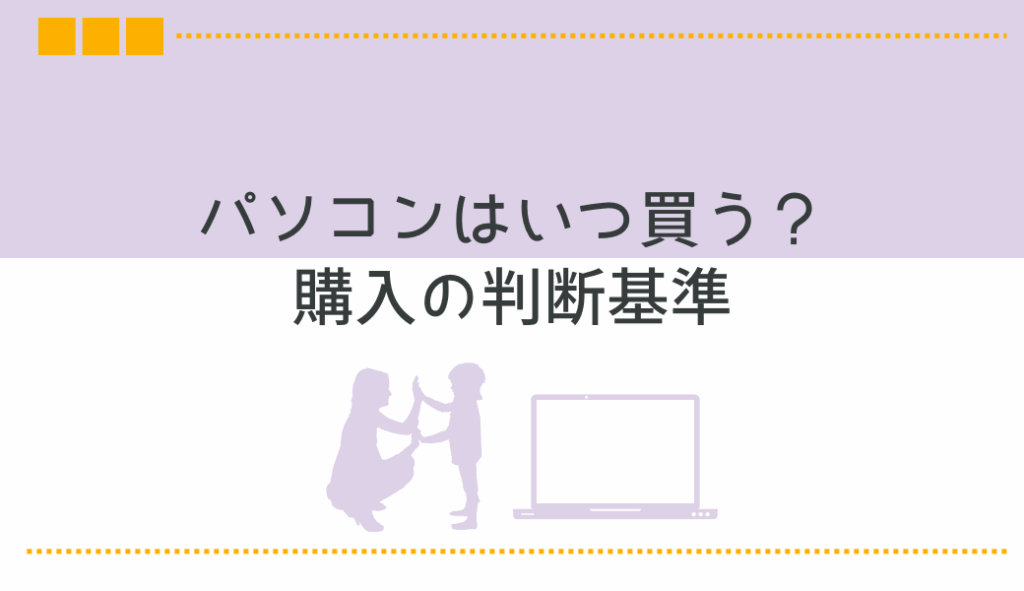
小学生の子供にパソコンを買うかどうか悩んだときは、
いつ買うのが良いのか?
というタイミングが大きなポイントになります。
無理に早く与える必要はありませんが、次のような条件に当てはまるときが購入の目安になります。
- 子供が強い興味を示したとき
- 習い事で必要になったとき
- 自宅学習を広げたいとき
子どもが強い興味を示したとき

パソコンでお絵描きしたい!

プログラミングでいろんなゲームを作りたい!

タイピングの検定を受けてみたい!
など、子供自身が具体的な目的や興味を持ち始めたタイミングがベストです。
興味がある時にパソコンを購入すれば、子供も一生懸命取り組んでくれるので、上達や理解がとても早いです。
習い事で必要になったとき
プログラミング教室や英会話、塾など、オンラインでも受講できる習い事が増えてきました。
オンラインでの習い事は、自宅にあるパソコンを使うことが一般的です。
習い事を始めるタイミングを購入の目安にするのもひとつでしょう。
自宅学習を広げたいとき
学校で配布されるパソコンは制限が多いため、自由に使うことが難しいのが現状です。
イラストソフトや動画編集、WordやExcelなどをお子様に自由に試させたい場合は、子供用に1台あると学びの幅が広がります。
我が家の体験談|年長で購入してからの活用例
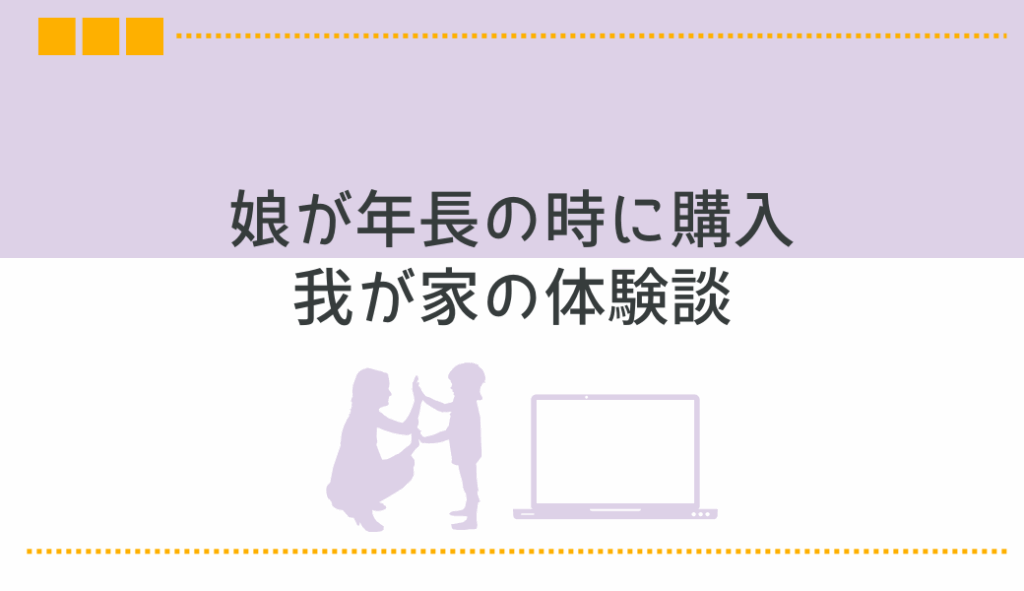
ここからは、実際に我が家でパソコンを購入したときの体験をシェアします。
上の子(娘)が年長のときに購入
娘が年長の時、私はパソコン教室で働いていて、自宅でもパソコン作業をすることが多々ありました。
パソコンで資料を作っている私の姿を見て、娘が「私もやってみたい」と(笑)
そこで、お絵描きソフトのペイントを使わせてみたところ、もともとお絵描きが大好きな娘は大喜び!
マウス操作はぎこちないものの、あっという間にペイントの操作方法を覚えて、夢中でお絵描きをし始めました。

パソコンは将来絶対使うし、お絵描きのスキルが将来役に立つことがあるかも知れない。娘用に1台買ってみても良いかも?
と思ったのが購入のきっかけです。


購入したのは上記のようなタブレットとノートパソコンが一体型になった2in1タイプ。キーボードやマウスは別売りのものを使っています。
小学4年生になった今の使い方
現在、娘は小学4年生になり、パソコンの活用の幅が大きく広がりました。
- Word→オンライン画像やテキストボックス、図形を使って簡単な文章が作れる
- Canva→メッセージカードや年賀状の作成
- ファイアアルパカ→ちょっと本格的なデジタルお絵描き
- Scratch・ビスケットプログラミング→簡単なゲームやアニメーション作成
他にも、小学1年生の下の子(息子)とはマイクラのゲームをして遊んだり、タイピングを競ったり、日々の生活の中で自然にパソコンを使っています。

娘とオンライン麻雀で対決を楽しんだこともあります(笑)
子供にパソコンを購入した体験から感じたこと
娘がペイントという新しい遊び(学び)に夢中になったタイミングでパソコンを購入したので、娘は自主的にどんどん使い方を覚えてくれました。
特別にタイピングが速いとか、絵が上手になったとか、そういう事ではありませんが、パソコンの基本的な操作や仕組みは、しっかり理解できているように思います。

変わらずお絵描きが大好きなので、オリジナルのLINEスタンプなんかも作れるようになったらいいなぁと思っています。
子供にパソコンを購入するメリット
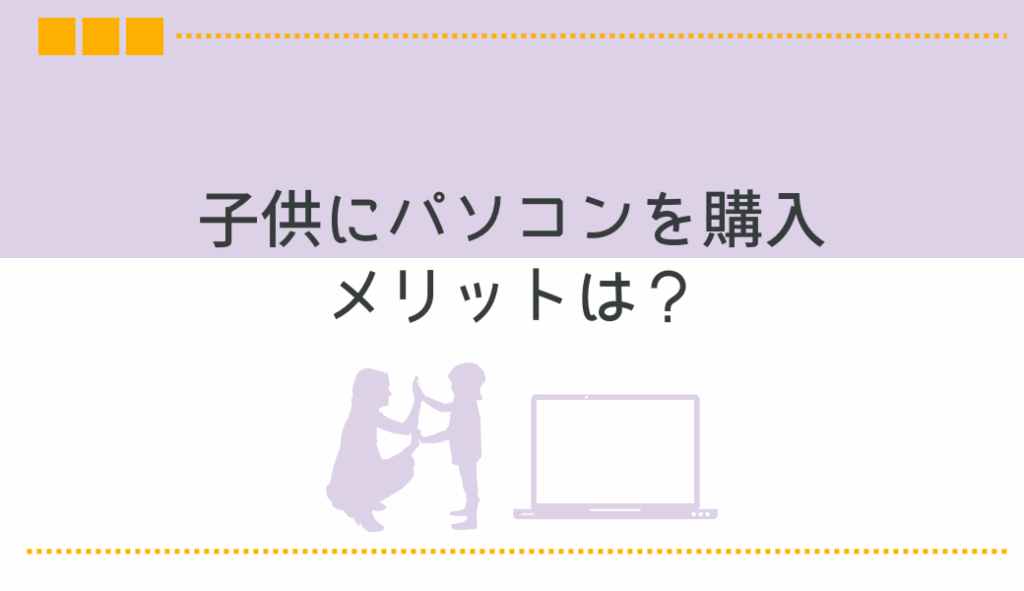
小学生にパソコンを買い与えることは、学習や生活の面で多くのプラスがあります。
ここでは代表的なメリットを紹介します。
学校の授業や宿題に強くなる
Wordで文章を書く、PowerPointで発表資料を作るなど、学校でもパソコンを使う場面は増えています。
自宅でパソコンに慣れていると、授業や宿題がスムーズに進められ、お子様の自信につながります。

我が家の子供たちが通う小学校では、3年生の時にPowerPointを使った学習発表会がありました。
情報活用力(ITリテラシー)が育つ
パソコンを使う経験を通して、子供たちは自然と 情報活用力(ITリテラシー) を身につけていきます。
これは、単にインターネットを使って検索できるという意味ではなく、情報を正しく扱い、必要に応じて整理・発信できる力を指します。
具体的には、次のような力です。
- 情報を正しく選び取る力
インターネットには正しい情報だけでなく、間違った情報や偏った意見も含まれています。検索を通じて複数の情報を比較し、自分に必要な情報を判断する習慣は、早いうちから身につけておきたい大切なスキルです。 - 情報を整理する力
調べた内容をWordにまとめたり、表や図を使って整理する練習を通じて、「情報を見やすく伝えるためにはどうすれば良いか?」を考える力が養われます。これは学校のレポートや発表、将来の仕事にも直結します。 - 情報を発信する力
パソコンを使ってスライドを作り、家族や友達の前で発表する体験は、単なるプレゼン練習にとどまらず、「自分の考えを相手に伝える」スキルを鍛える場になります。 - デジタル社会を生きる基礎
今の子供たちが大人になる頃には、仕事も生活も今以上にデジタル化されているでしょう。小学生のうちから「正しく情報を扱う感覚」を身につけておくことは、安心してデジタル社会を生きるための土台になります。
自主的な学びにつながる
「調べたい」「作りたい」と思ったときに、自宅で自由に使えるパソコンがあると、子供たちは自分から学びを深めていきます。
与えられる勉強ではなく、自分で学ぶ姿勢が自然と身につきます。

娘は小2の時に、Googleのストリートビューでヴェルサイユ宮殿を知りました。そこからヨーロッパの歴史に興味を持ったようで、インターネットを使ってよく調べています。
創作や表現の幅が広がる
ペイントやイラストソフト、音楽制作ソフトなどを使えば、子どもの「やってみたい!」を自由に形にできます。
紙と鉛筆だけではできない表現がパソコンを使う事でできるので、創造力や表現力を大きく伸ばせます。

子供の可能性は無限大!
子供にパソコンを購入するデメリットと注意点
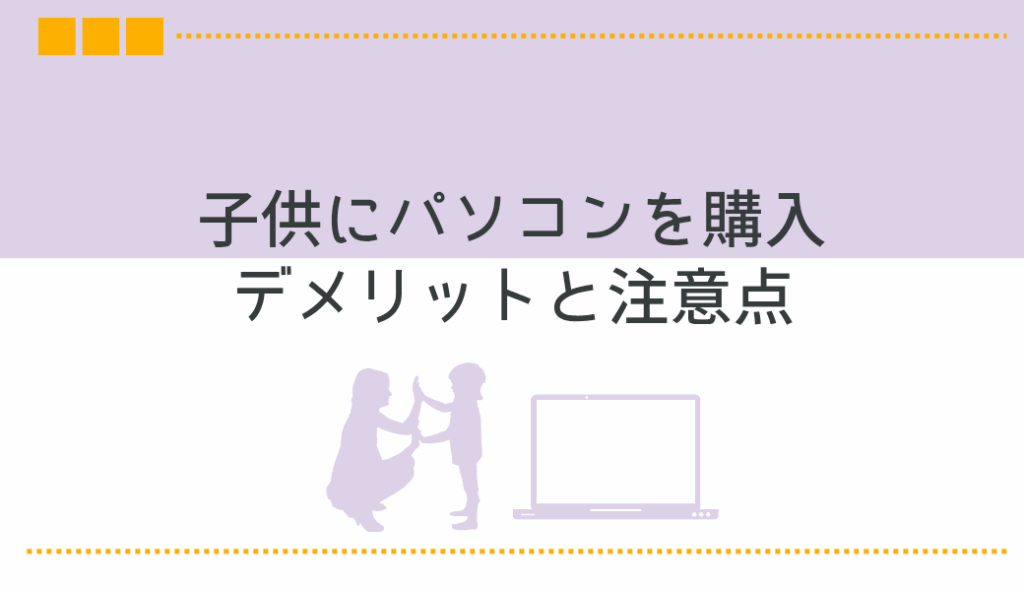
パソコンを持つことで学びや可能性が広がる一方で、注意しておきたい点もあります。
ここでは、デメリットと注意点をセットで整理してみましょう。
ゲームや動画に使いすぎるリスク
YouTubeやオンラインゲームは魅力的ですが、長時間の利用は学習や生活リズムに悪影響を与える可能性があります。
対策: 利用時間のルールを決めて、親子で「約束」を共有しておくことが大切です。
金額的な負担がある
パソコンは安い買い物ではなく、子どもが小さいうちは「壊してしまわないか」という心配もあります。
対策: ハイスペックなパソコンの購入は控えましょう。また、パソコンは精密機器で、雑な扱いをするとすぐに壊れてしまうことをしっかりお子様に伝えましょう。
ネットトラブルやセキュリティの心配
インターネットを自由に使えるようになると、不適切なサイトや不審なリンクをクリックしてしまうリスクもあります。
対策: フィルタリングやウイルス対策ソフトを導入することに加え、日常的に「ネットで困ったことがあったら必ず相談する」という習慣を作っておくことが大切です。
姿勢や視力への影響
長時間画面を見続けると、姿勢の悪化や視力低下につながることもあります。
対策: 使用時間を区切る、机や椅子の高さを調整するなど、環境を整えてあげましょう。

我が家の子供たちは、夢中になると、ついつい画面に顔を近づけてしまうので、注意して見守るようにしています。
小学生におすすめのパソコンスペック
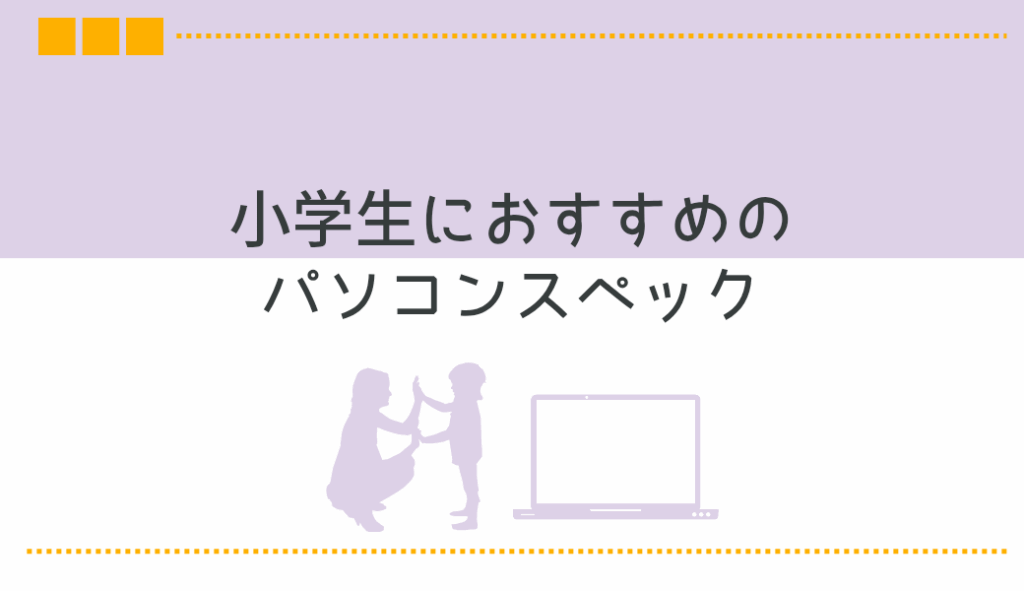
パソコンといっても種類が多く、安価なものから高性能なハイスペックモデルまで幅広くあります。
「子ども用だから一番安いものを…」と購入される方もいますが、あまりに低スペックだと動作が遅く、使えない場合があります。
逆に高すぎるスペックは小学生には不要です。
ここでは、学習や創作に安心して使える標準的なスペックを紹介します。

ノートパソコンの寿命は5年くらいと言われることが多いので、5年先まで使うイメージで選びましょう!
OS(基本ソフト)
パソコンを選ぶ時に、まず、重要になってくるのがOSと呼ばれるパソコンの基本ソフトです。
パソコンのOSは主に
- Windows
- MacOS
- ChromeOS
があり、日本の企業やプログラミング教室などで一般的に使われているパソコンの多くはWindowsです。

学校で配布されているパソコンはChromeOSが多いね!
Windowsのパソコンは、WordやExcelのofficeソフトと相性がよく、様々なメーカーから販売されているので、価格帯やデザインの選択肢が豊富です。
MacOSのパソコンは、apple社のMacシリーズに搭載されているOSです。
iPhoneやiPadとの連携がスムーズで、イラスト・音楽・動画制作などの クリエイティブな作業に強いことが特徴です。

我が家ではWindowsのパソコンを購入しました。子供たちが将来的にクリエイティブな方面に進みたいということになれば、MacOSのパソコンを購入すると思います。
CPU(処理の速さを決める部分)
OSが決まったら、次はCPUを決めましょう。
CPU(シーピーユー)は、パソコンの「頭脳」といえる部分で、処理の速さや快適さに大きく影響します。
小学生向けに購入する場合でも、最低限の性能を押さえておくことが大切です。
CPUの主な種類は下記になります。
- Intel(インテル)
- AMD(エーエムディー)
それぞれの性能にランクがあり、数字が大きくなるにつれて性能が高くなります。
選び方の目安
- Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 以上
→ 調べ学習、Word・Excel、Scratchや簡単なイラスト制作なら十分 - Intel Core i5 / AMD Ryzen 5
→ 簡単な動画編集、3Dゲーム(マイクラJava版など)、画像加工なども快適 - Intel Core i7 / AMD Ryzen 7
→ プロレベルの動画編集やプログラミングを想定するなら必要、小学生にはちょっとオーバースペック

小学生の学習用なら Core i3/Ryzen 3 以上で十分、余裕があれば Core i5/Ryzen 5を選ぶ がおすすめ!

選ぶ時の注意点は、CeleronやPentiumなど廉価なCPUを避けることです。安く購入できますが、動作が重くなりやすく、数年で使いにくくなる可能性が高いです。
メモリ(作業の快適さに直結する部分)
メモリは、パソコンが同時にどれだけの作業をスムーズに処理できるかを決める重要な部分です。
机の広さに例えられることも多く、「広い机ほど作業が快適」というイメージを持つと分かりやすいです。
おすすめのメモリ容量
- 8GB以上が必須
→ 学校で使うWordやExcel、インターネット検索、Scratchなどのプログラミング学習なら問題なく動きます。 - 16GBあるとより快適
→ マインクラフト(Java版)やイラスト制作ソフト、動画編集などを並行して使う場合でもスムーズに動作します。 - 4GB以下はおすすめしない
→ 値段は安くても、複数のアプリを開くとすぐに動作が重くなり、イライラして学習意欲を損なう可能性があります。

小学生から使い始めて、中学・高校まで長く使うことを考えれば 最低8GB、できれば16GB を選んでおくと安心!

我が家では8GBを購入しました。中学生や高校生になると16GBが安心かなと感じています。
ストレージ(データ保存)
ストレージは、パソコンの中でデータやアプリを保存する「引き出し」のような部分です。
容量や種類によって、使いやすさが大きく変わります。
ストレージの主な種類は下記になります。
- SSD(ソリッドステートドライブ)
- HDD(ハードディスクドライブ)

おすすめはSSD!!

HDDのパソコンは安価ですが、動きが遅いので作業効率がかなり悪いです。Windowsの更新にも半日~1日かかる事もあります。
SSDの容量の目安
- 256GB以上あれば安心
- 512GB以上あると余裕があり、動画編集やマイクラの大きなデータ保存にも対応可能
- 128GB以下はすぐにいっぱいになり、Windowsの更新やアプリの追加で動作に支障が出やすい

娘のパソコンのSSDは128GBです。Windowsの更新にはHDDほどではないですが、確かに時間がかかり、不便に感じることが時々あります。
おすすめのスペックをまとめると
ここまででご紹介した、小学生におすすめのスペックをまとめると下記のようになります。
| OS (基本ソフト) | ・学校での学習や標準的な使い方 → Windowsが安心 ・デザイン・創作活動やApple環境に合わせたい → macOSが快適 |
| CPU (処理の速さを決める部分) | ・Core i3/Ryzen 3 以上で十分、余裕があれば Core i5/Ryzen 5を選ぶ |
| メモリ (作業の快適さ) | ・最低8GB、できれば16GBを選んでおくと安心 |
| メモリ (作業の快適さ) | ・SSDで256GB以上あれば安心 |
我が家で購入した娘のパソコンは、CPUとストレージが上記より少し低いスペックになります。
年長・小1くらいの「遊び」感覚で使っている時は問題なかったですが、小3くらいから発展的な学習をするようになって、少し動作が遅かったり、更新に時間がかかったりと、不便を感じるようになりました。
スペック以外に気をつけるポイント
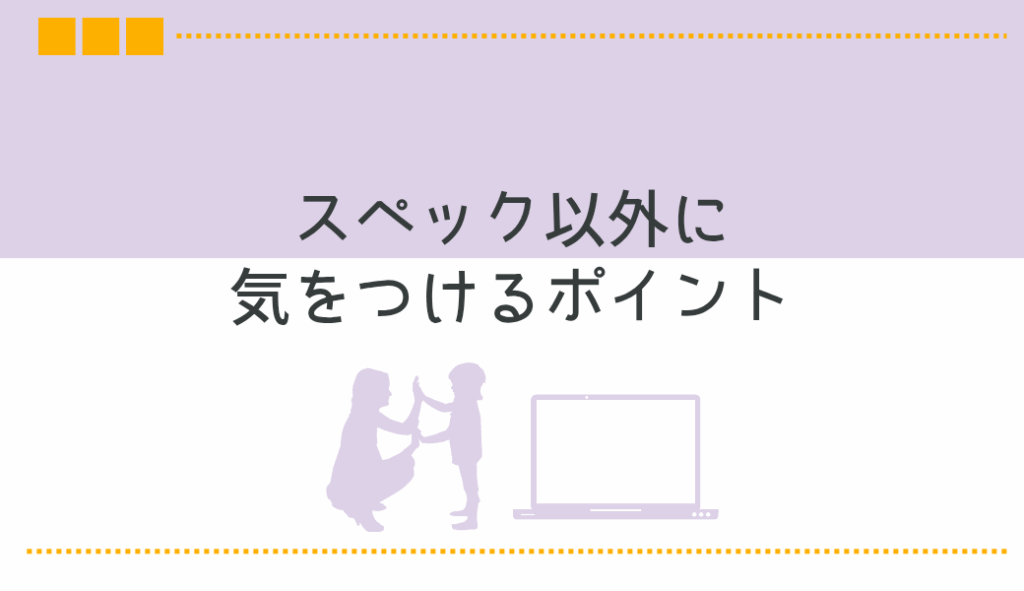
スペック以外にも気をつけるポイントがあるので、ご紹介していきます。
画面のサイズと重さ
小学生用のパソコンを選ぶときは、「画面の見やすさ」と「持ち運びやすさ」のバランスが大切です。
特に家庭学習だけでなく、習い事や外出先に持っていく可能性を考えると、サイズや重さは重要なポイントになります。
画面のサイズの目安
- 12〜14インチ
→小学生にちょうど良いサイズ感。軽量で持ち運びしやすく、机の上でも場所を取らない。 - 15インチ以上
→画面が大きく見やすいので、文章作成やイラスト制作に向く、ただし重いので持ち運びが不便。 - 11インチ以下
→小型で軽いが、文字や画面が小さくなり、見づらいことも。

1番おすすめなのは、持ち運びしやすい12~14インチのノートパソコンです。
タッチパネル対応

娘のパソコンは10.5インチと小さめです。今のところ不便はありませんが、Excelを使うようになったり、繊細なイラストを描くようになると、もう少し画面の大きいパソコンの方が便利かなと感じています。
最近では、タブレットのように指で操作できるタイプのパソコンも販売されています。
低学年のお子様は手が小さいので、マウス操作に慣れるまでに時間がかかる場合があります。
その点、タッチパネル対応のパソコンなら、小さいお子様でも直感的に操作できるのでおすすめです。
キーボードの使いやすさ
子供の手でも押しやすく、打鍵感がしっかりしているものが理想です。
安価なPCだと、キーが小さすぎたり浅すぎたりして打ちにくいことがあります。

娘が使っているのは、Logicoolのキーボードです。全体的に少し小さめで、子供や女性が使いやすいサイズ感だと感じています。


キーボードには、タイピングの指の位置が覚えられるように、指ごとに色を分けてシールを貼っています。
価格帯の目安
小学生が使うパソコンを選ぶ際に気になるのが「どのくらいの価格帯が適切か?」という点です。
結論から言うと、できれば10万円以下のノートパソコンで、おすすめのスペックの条件を満たしておればベストです。

娘のパソコンは8万円弱で購入しました。最近は物価高なので、全体的にもう少し価格が上がっているかも😿
5万円以下の低価格帯のパソコンも販売されていますが、スペックが低く、動作が遅くなりやすいので注意です。
中古のパソコンには注意!
また、中古で販売されているパソコンを購入する際も注意が必要です。
「あまりパソコンに詳しくない」という方は、中古のパソコンは避ける方が良いでしょう。
私がパソコン教室で働いていた時に、中古のパソコンを購入して失敗した!というお声を何度か聞いたことがあります。
- WordやExcelなどofficeが入っていなかった
- 1年も経たないうちにバッテリーの寿命がきて使えなくなった
- Microsoft officeではなく、WPS officeが入っていて使いにくかった
- WiFiのないパソコンだった など
まとめ
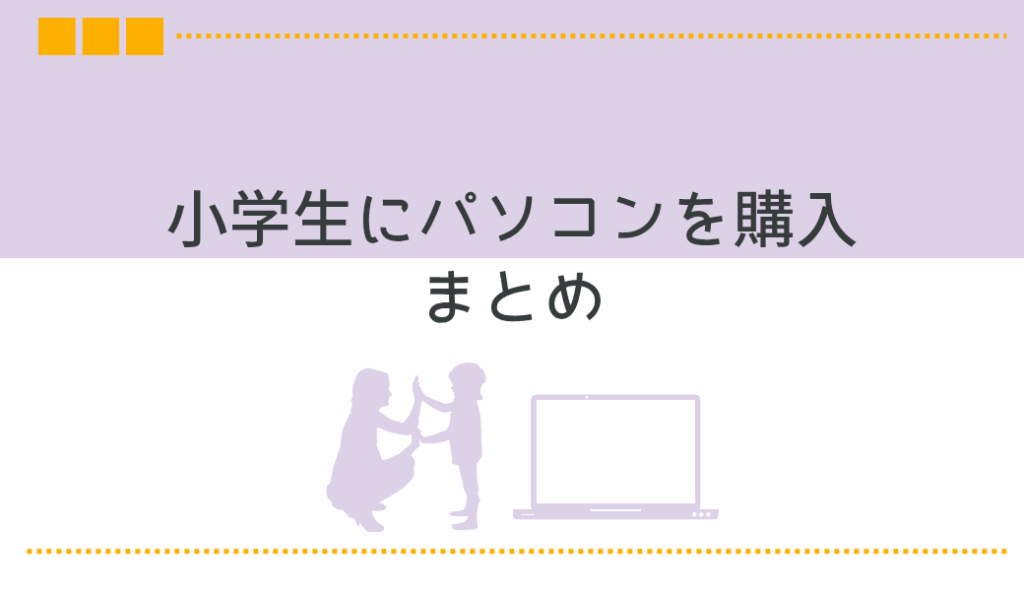
小学生にパソコンを買うべきかどうかは、ご家庭の学習スタイルやお子様の興味によって答えが変わります。
学校で配布されるパソコンだけでも最低限の学習は可能ですが、自由に使える自宅用パソコンがあると
- 調べ学習
- プログラミング
- 学習発表のスライド作り
- デジタルお絵描き
など、子供の可能性を大きく広げることができます。

急いで買う必要はないけど、お子様が興味を持ったタイミングで購入するのがベスト!
最も大切なのは、パソコンをただ「与える」だけでなく、保護者が見守り、ルールを一緒に決めて活用することです。
ご家庭に1台のパソコンがあれば、子供の学びの幅は大きく広がり、将来につながる力を育てるきっかけになります。
今回は、小学生にパソコンを購入するべきかについて、詳しくまとめました。
ぜひ、参考にしていただけると嬉しいです。
それでは、最後までご覧くださり、ありがとうございました!
小学生におすすめのプログラミング教室を項目別にまとめました